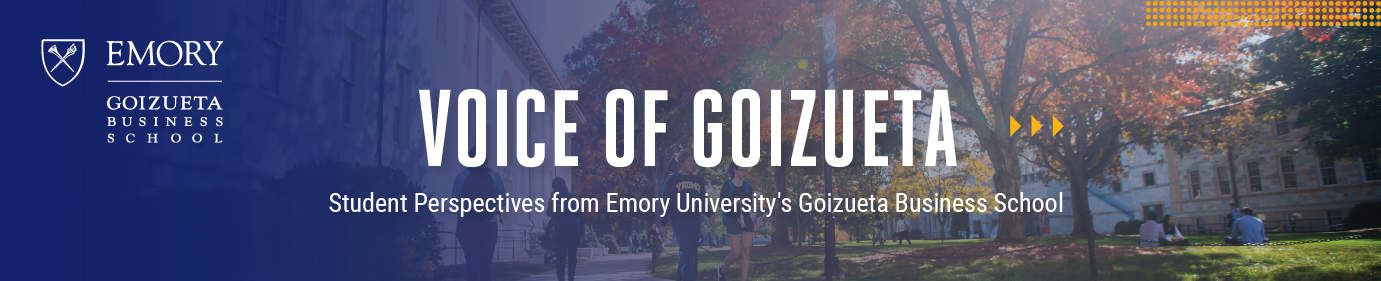デルタ・リーダーシップ・コーチング・フェロー・プログラムから学んだ6つの教訓

最近、Center for Creative Leadershipの記事で、初めて管理職になった人の約60%が正式なトレーニングを受けていないことを知りました。 1年以上前に初めて管理職になったとき、当時デルタ航空のリーダーシップ・コーチング・フェロー・プログラムで学んだフレームワークを適用することが役に立ち、この教訓を他の人の役に立てればと思い、シェアしたいと思いました。 本プログラムはマネージャートレーニングを目的としたものではありませんが、コンセプトは重なる部分が多くあります。
LCFプログラムをご存じない方のために説明すると、フェローはMBAの2年生で、1年生からなるチームのチームダイナミクスやピアフィードバックを指導します。 コーチングに備えるための継続的なトレーニングの一環として、セミナーやエグゼクティブ・コーチが個別に対応してくれたのです。
プログラムの教訓をいくつか。
- “チームを知れ –個人的に“。これは、ゴイズエタのリーダー育成プログラムの副学部長であるケン・キーン元教授が、LCFの最初のワークショップで語った言葉で、私の心に強く残っています。 LCFのプロセスの一環として、コーチはコーチングを受けるチームの各メンバーと1対1で会い、相互のフィードバックを確認しました。 私たちは、自分が話したことの2倍、あるいはそれ以上、耳を傾けるように教えられました。 そこで、これらの学びを組み合わせて、スタッフ一人ひとりとの1対1の面談を設定したのです。 週1回のチェックイン型ミーティングのことではありません(私もやっています)。 オフィスから出て、コーヒーを飲みながら、携帯電話の電源を切って相手の目を見て、テーブルの向こう側にいるこの人がどんな人なのか、本当に耳を傾けてみるということです。 あなたが本当に気にかけていることが伝われば、チームから信頼を得ることができます。
- 信頼関係を構築し、心理的な安全性を確保する。 新任のマネージャーとなれば、懐疑的な見方をされるのは目に見えていた。 そこで私は、チームが信じてくれるまで、毎日根気よく私と一緒なら安全だということを示すことを自分の使命としたのです。 “心理的安全 “や “安全の輪 “と呼ばれるものを聞いたことがあるかもしれませんね。 基本的な考え方は、チームメンバー間の信頼がなければ、チームメンバーは(正当かどうかは別として)仕事をするために使うべき不必要なエネルギーをお互いに防衛することになる、ということです。 そのためのもう一つの重要な要素は「弱さ」であり、これはまずリーダーから丁寧にふりかける必要があります。 リーダーが適切に弱音を吐くことができると分かれば、チームも安心して間違いを認めたり、助けが必要だと思ったりするようになります。
- 期待値を設定し、頻繁に報告する。 私たちLCFは、期待値設定セッション(アクションレビュー前)と報告セッション(アクションレビュー後)を通じて、チームを指導する役割を担っています。 私自身、学生時代のチーム活動でその価値を実感していましたが、職場でも十分に通用することがわかりました。 なぜ毎日出勤するのか、お互いに何を期待しているのか、どうすればもっと良くなるのか、などを話し合いました。
- チームビルディングのための時間をとる。 私が入社したころは、月1回のチームミーティングがあり、時にはゲストスピーカーを招いての勉強会などもありました。 私は、仕事に関するトピックを取り上げ、知識とスキルを高め、互いをより深く知るための十分な時間を確保するため、これを2回のミーティングに分けることを提案しました。 これはLCFのもう一つの重要な教訓で、仕事以外の時間を使って絆を深めることは、何か対立や疑問が生じたときに大きな利益をもたらすのです。
- “フィードバックはギフトである”これはLCFプログラムのモットーであり、特にリーダーには当てはまります。 ランクが上がれば上がるほど、フィードバックが少なくなる。 権威的な役割を担うということの固有の性質として、たとえ良好な関係を築いていても、他人はオープンで正直な気持ちを持つことをためらいがちです。 フィードバックはまさに贈り物です。自分の盲点を明らかにし、良い行動を強化し、自分を成長させるのに役立ちます。 それを率直に、頻繁に求める。
- チームを指導する。 チームメンバーには個人的な能力開発が必要であり、それはコーチングによく似ています。 コーチとして学んだスキルや、エグゼクティブ・コーチからの観察をもとに、トレーニングの機会を提供し、チームが課題を解決できるようサポートしました。 彼らが問題を解決する方法を学べば学ぶほど、現在の仕事、そして将来の仕事で力を発揮することができます。
私のチームと私には、ある意味でファイターであり、サバイバーであるという大きな共通点があります。 最終的に、私たちの成功は、非常にシンプルでありながら見落とされがちな、「同僚は第一に人間であり、第二に従業員である」という考えに行き着いたのです。